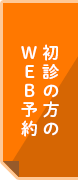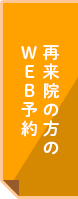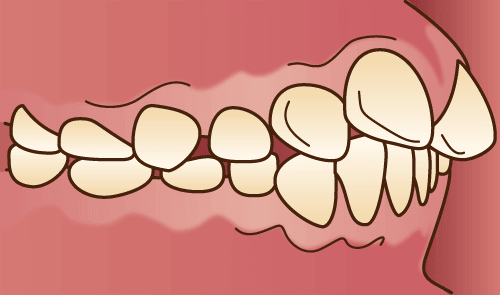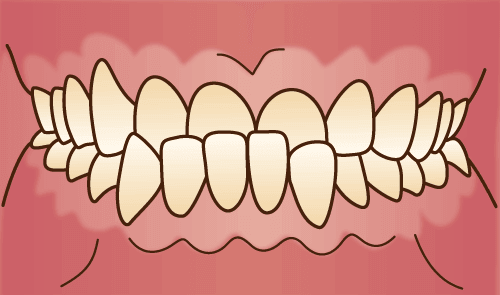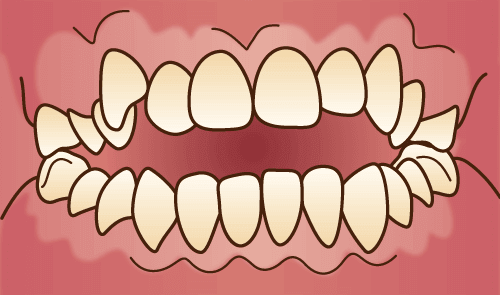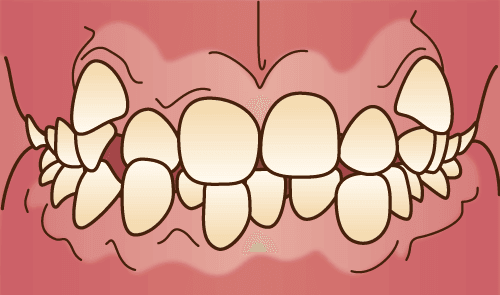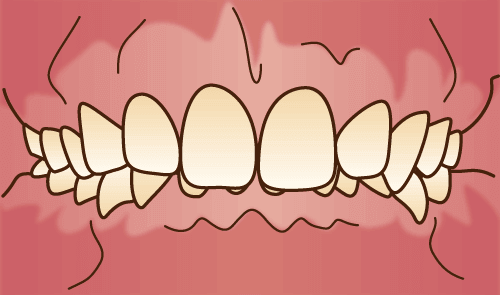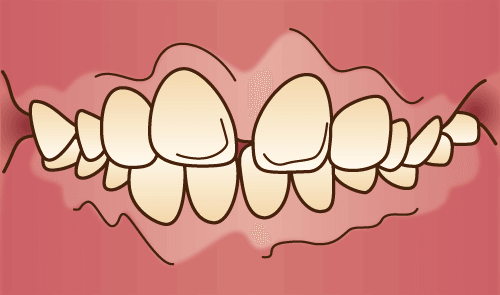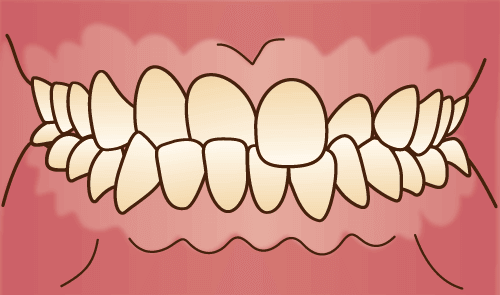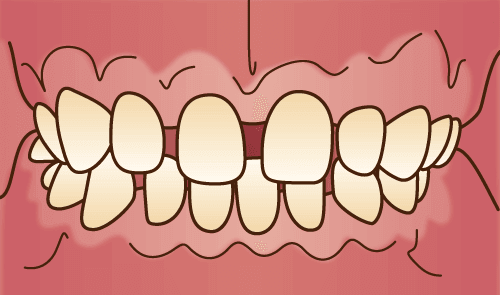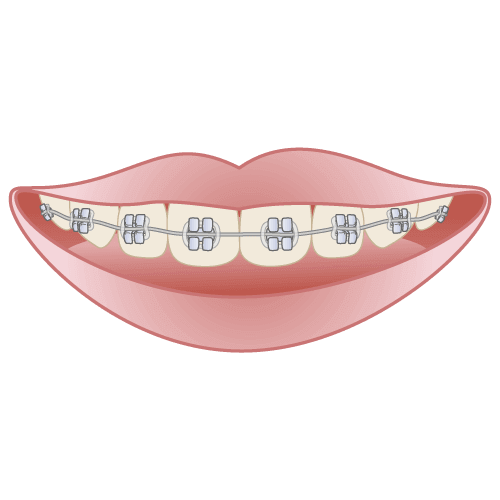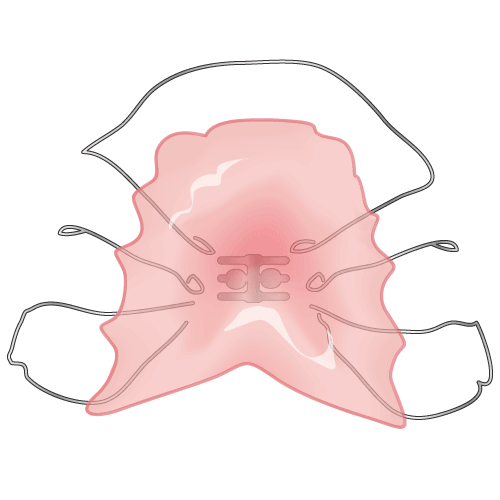矯正治療のメリット・デメリット
メリット
- 歯並びが良くなることで、笑ったときの印象が変わり、外見のコンプレックス解消に繋がる
- 歯磨きがしやすくなり、虫歯や歯周病のリスクを下げることができる
- お口の清掃がしやすくなるので口臭改善になる
- 噛み合わせ改善により顎関節症や偏頭痛の改善が見込まれる
- 均等に歯が接することでお顔のバランスが良くなる
デメリット
- 口を開けた時に、治療中の装置が見えてしまうものもある
- 装置をつけていると、慣れるまでは話しづらい
- 装置の間にカスが溜まりやすいので、より丁寧な歯磨きが必要になる
- 装置を使って少しずつ歯を動かすので、じわっとした痛みがある
- 治療期間が長め
- 治療費が他の診療に比べて高価である